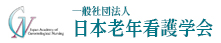国際交流委員会から国際誌掲載論文のご紹介

この企画は,本学会会員の皆様の看護実践や研究活動等に役立つと思われる国際誌掲載論文を紹介することを目的としています.高齢者の生活施設で勤務する看護師の団体であるAmerican Assisted Living Nurses Associationと老年看護の高度実践看護師の団体であるGerontological Advanced Practice Nurses Associationの公式雑誌であるGeriatric Nursing誌に加え,看護学全般の国際的な主要ジャーナルの一つであるInternational Journal of Nursing Studies誌から1回につき合計3つの論文のタイトルと要旨を翻訳しご紹介します.ご紹介する論文は両誌の最新巻から,文化が類似していて,日本の実践・研究に参考にしやすいと思われる東アジア圏(日本,中国,韓国,台湾等)の著者の論文を主に選定します.
今後,2か月に1回程度ご紹介する予定です.会員の皆様に興味を持っていただけそうな論文を選んで紹介させていただきます.関心のあるテーマなどございましたら,お知らせください.
日本老年看護学会国際交流委員会
INDEX
Vol.18
1.縦断的研究
Factors influencing activities of daily living in community-dwelling older adults with dementia
地域在住の認知症高齢者の日常生活動作に影響を与える要因
Jungwon Cho, Eunhee Cho, Minhee Yang, Eunkyo Kim, Sinwoo Hwang
Geriatric Nursing 66, 2025.
URL:
https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2025.103627
要旨
本研究は、地域在住の認知症高齢者の日常生活動作(ADL)のレベル、ADLへ影響を与える要因、及びADLの変化を明らかにすることを目的とした。韓国の地域在住認知症高齢者186名のデータを分析し、そのうちの63名に対してADLの変化とその影響要因を明らかにするために12ヶ月後に追跡調査を行った。ADLは韓国版ADL尺度(K-ADL)を用いて測定し、認知機能や認知症の行動・心理症状との関連は、重回帰分析、一般化推定方程式を用いて分析した。その結果、特にトイレの使用および排便・排尿のコントロールにおいて、ADLの遂行に依存があることが示され、これらは1年後に有意に悪化していた。また、血管性認知症であることや、認知症の重症度が高まることによりADLの自立度が低くなることが示された。
これらの結果は、ADLの自立度が低下しやすい高齢者の早期発見の可能性を示すとともに、認知症高齢者が地域で生活を続けられるよう支援するために、在宅および地域を基盤としたケアサービスの開発が急務であることを示唆している。
国際交流委員会コメント
本研究は、地域在住の認知症高齢者のADLの変化を経時的に追跡調査することで、維持することが困難なADLの種類や、ADLへ影響を与える要因を特定することを目的として実施されました。認知症高齢者が住み慣れた地域でその人らしい豊かな生活を継続するためには、ケア提供者は認知症の種類や重症度により今後起こりうるADLの変化を予測しながら、生活全体を支え、環境を整えていくことが大切です。とりわけ、本研究により様々なADLのなかでも、自尊心の低下に大きく関わる排尿・排便に関するADLが有意に悪化することが明らかにされたことにより、その点を配慮した関わりや新たな支援サービスの開発および評価が急務であると感じます。
2.横断的研究
Association between driving status and visiting places among older adults in a suburban area in Japan: Findings from a cross-sectional survey
日本の郊外地域に居住する高齢者における運転状況と訪問先との関連:横断研究による検討
Taiji Noguchi, Ayane Komatsu, Sayaka Okahashi, Takeshi Nakagawa, Xueying Jin, Yumi Shindo, Tami Saito
Geriatric Nursing 66, 2025.
URL:
https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2025.103626
要旨
本研究では、運転状況によって訪問先の種類や数が異なるかを検討するとともに、代替交通手段の利用がこの関連に影響するかどうかについて検討した。本研究には、日本の郊外地域に居住し、日常生活動作が自立している65歳以上の地域在住高齢者432名(平均年齢74.8歳、女性52.8%)が参加し、郵送による自己記入式質問票を用いてデータを収集した。多変量回帰分析の結果、非運転者は運転者に比べて訪問先の種類が有意に少ないことが明らかとなった。特に、消費・行政・セルフケアに関連する生活関連施設、社会・文化・宗教的活動に関連する場所において顕著であった。さらに、鉄道・バス等の公共交通機関の利用は、非運転者における訪問先減少の影響を有意に緩和することが示された。
これらの知見より、運転の制限は高齢者の訪問先、とりわけ生活関連施設や社会・文化活動施設への訪問を減少させる可能性が示唆され、代替交通手段の整備が重要であることが考えられる。
国際交流委員会コメント
本研究により、日本の郊外地域に居住している高齢者では、運転をしていない場合、特に生活関連(スーパー、銀行、役所など)や社会・文化的な(友人宅、レストランなど)場所の訪問が大きく制限され、生活範囲が縮小しやすいことが明らかにされました。また、家族の送迎は、心理的負担や時間的制約があるために、訪問場所を大きく増加させる補完的な手段とはなりにくいと考えられます。生活範囲の縮小は、高齢者の社会参加の低下に繋がり、生活の質の低下や心身の健康にも影響を及ぼす可能性も示唆されます。高齢者に優しい街づくりにおいて、公共交通機関の整備や、AI技術等を活用した代替交通手段の開発・社会参加の維持が喫緊の課題と言えるでしょう。
3.混合研究法
Determinants of preparation for future care among community-dwelling older adults with chronic diseases: A mixed-method study
慢性疾患を有する地域在住高齢者における将来のケア準備に対する規定因子:混合研究法による検討
QiqiNi, LiWang, WeijingSui, YiyuZhuang
Geriatric Nursing 66, 2025.
URL:
https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2025.103704
要旨
本研究の目的は、慢性疾患を有する地域在住高齢者における将来のケア準備(preparation for future care : PFC)に影響を及ぼす要因を明らかにすることであった。研究デザインは、混合研究法を使用し、量的データは重回帰分析およびネットワーク分析を用いて分析し、質的データは演繹的テーマ分析により検討した。さらに、両データの知見は、Andersen の医療サービス利用行動モデルを枠組みとして統合した。
量的データとしては、PFCを評価するためにPreparation for Future Care Needs Scale(PFCN)を使用し、Health Literacy Management Scale(HeLMS)、Family APGAR(Family Adaptation, Partnership, Growth, Affection, Resolve)、Chronic Illness Resource Survey Scale(CIRS)、10-item Connor–Davidson Resilience Scale(CD-RISC-10)、Brief Illness Perception Questionnaire(BIPQ)を用いて、健康状態、セルフマネジメント、家族や社会的支援などの影響要因を測定した。質的データとしては、半構造化インタビューによりPFC に関する認識、動機、阻害要因を深く探求した。
最終的に、量的研究には362名、質的研究には16名の高齢者が参加し、統合の結果、将来のケア準備に影響する多次元的要因として、3つの主要テーマと9つのサブテーマが抽出された。それらは、1.素因因子(predisposing factors): 孝行観(filial piety)に関する信念、家族構成、年齢、ヘルスリテラシー・2.実現因子(enabling factors): 介護資源、経済状況、社会的支援・3.ニード因子(need factors): 身体的健康、精神的健康であった。慢性疾患をもつ地域在住高齢者の PFC は、多段階的かつ多面的なプロセスであり、心理的・家族的・社会的要因が複合的に影響していた。本研究の結果は、慢性疾患を有する高齢者が将来の介護に主体的に備えることを促進するためには、伝統的価値観への対応、家族および社会的支援システムの強化、ならびに介護資源へのアクセス性および質の向上を図るための戦略が必要であることを示唆している。
国際交流委員会コメント
本研究では、混合研究法を用いることで、慢性疾患を有する地域在住高齢者のPFCには、心理的・家族的・社会的要因が複合的に影響していることが明らかになりました。PFCを測定するために用いられたPFCN尺度は、認識(awareness)、適切な計画(correct planning)、意思決定(decision-making)、および 回避(avoidance) の4つの下位尺度から構成され、合計14項目で構成されています。総得点は 14〜70点 の範囲を取り、得点が高いほど、将来のケアに対する準備度が高いことを示しています。本研究は中国で実施されましたが、独居高齢者が増加し、家族の在り方が多様化する日本においても同様に、高齢者自身が将来のケアに備えることができるための情報提供や不安の軽減など、地域資源へのアクセスの向上を含めた包括的な介入の整備が、喫緊の課題であると思われます。